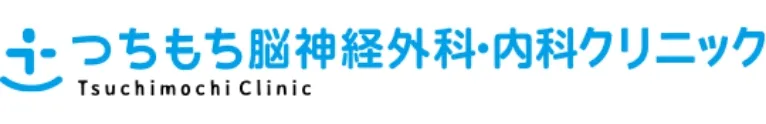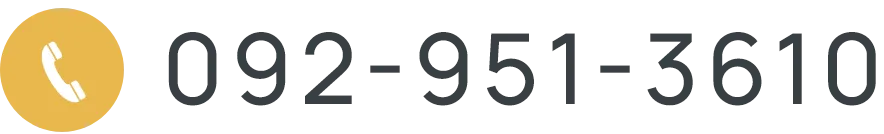起こる前に防ぎ、再発させない。脳卒中は予防が重要です。
脳卒中とは
「脳梗塞」「脳内出血」「くも膜下出血」の3つの病気を総称し、一般に脳卒中と呼んでいます。
これらは突然発症し、たとえ回復しても手足の麻痺や言語障害、認知症などの重篤な後遺症を残すことが多く、最悪の場合は死亡したり寝たきりとなることもあります。
そのため予防が大変重要です。
脳梗塞
脳梗塞とは、脳の動脈が何らかの原因で狭窄や閉塞を起こすことで、その動脈の支配する領域の脳組織に十分な酸素・栄養が行かなくなり、脳が機能障害や壊死に陥る状態をいいます。
脳内出血
脳内血とは、脳内の血管が何らかの原因で破れ、脳内に出血した状態をいいます。
それにより、意識や感覚への障害、運動麻痺などの症状が現れます。
出血によって脳幹部が圧迫された場合は、死に至ります。
くも膜下出血
脳は外側から、「硬膜」「くも膜」「軟膜」という3枚の膜で覆われた構造となっています。
くも膜下出血はくも膜の内側に出血し、死亡率の高い病気です。
働き盛りの人によく起こることも特徴の一つです。
脳卒中の原因
脳梗塞の危険因子は「高血圧」「糖尿病」「脂質異常症」「心臓病」「ストレス」「喫煙」「大量飲酒」「脱水」「肥満」などさまざまなものがありますが、いずれも生活習慣に関係するものです。
脳内出血の多くは高血圧が原因であり、動脈硬化を基盤とした病変に小さな血管のこぶのようなものができ、その破裂が脳出血を引き起こします。
くも膜下出血の原因でもっとも多いのは、脳の太い動脈が膨れてできるこぶのような脳動脈瘤の破裂です。
ついで脳動静脈奇形による出血、頭部外傷などがあります。
次に脳動静脈奇形による出血、頭部外傷などがあります。
脳卒中の症状
脳梗塞
- 片側の手足や顔面の麻痺・感覚障害
- 言語の異常(言葉が出てこない、会話を理解できないなど)
- 視覚異常(視野が狭くなる、ものが二重に見えるなど)
- 食べたものがこぼれる、うまく飲み込めない
- ふらつく
脳内出血
- 激しい頭痛
- 嘔吐
- 意識障害
- 言語の異常(言葉が出てこない、会話を理解できないなど)
- 回転性のめまい
くも膜下出血
- 突然の激しい頭痛
- 吐き気・嘔吐
- 頸の後ろ(うなじ)がこる
- 意識がもうろうとしている、反応が鈍い
- 片側の手足の麻痺
当院での治療

当院に来院され、容態から脳卒中と診断した場合は、手術・入院設備のある医療機関をご紹介いたしますが、ご自宅または外出先で急を要すると思われる場合は、迷わず救急車を呼んでください。
近年よく話題となる、何も症状が出ていない「かくれ脳梗塞」の場合は、内科的な薬物療法が主体になるため、当院で治療を行います。
脳卒中は再発することも多いため、当院では、脳卒中の発症に関わる高血圧・脂質異常症(高脂血症)、高コレステロール血症、糖尿病など、危険因子の治療、管理を行い、脳卒中の予防や再発予防に力を入れています。
よくある質問
- Q
脳卒中を予防するにはどうすればよいですか?
- A
脳卒中の発症には「高血圧」「脂質異常症(高脂血症)」「高コレステロール血症」「糖尿病」などが深く関わっており、これら危険因子の適切な治療が必要です。
危険因子の適切な治療、管理を行うとともに、食事や運動など生活習慣も見直し、改善することが重要です。
- Q
頭痛持ちで脳卒中かなとときどき心配になります。危険な頭痛を教えてください。
- A
くも膜下出血は、突然起こる経験したことがないような激しい頭痛が特徴です。
頭痛に加え、「嘔吐」「意識消失」「めまい」などが加われば、くも膜下出血が強く疑われます。
脳梗塞、脳内出血は多くが手足の麻痺や言語障害を伴います。
脳梗塞では通常頭痛が起きないので注意が必要です。
- Q
祖父が脳卒中で倒れたので、とても怖いです。脳卒中は遺伝するのでしょうか?
- A
くも膜下出血は、その7~8割が脳に血液を送る太い動脈の一部が膨らんだ動脈瘤の破裂によって起こります。
脳動脈瘤は家族内発生が報告されており、家族にくも膜下出血になった方、動脈瘤を観察中の方がいる場合は、一度早めに受診されることをおすすめいたします。
頭痛
命に関わる危険な頭痛の特徴を知っておきましょう。
頭痛の種類と原因
頭痛は、頭痛そのものが治療の対象となる慢性的な頭痛と、脳の病気に伴う二次的な頭痛の2タイプがあります。
慢性頭痛
慢性的な頭痛は、「緊張型頭痛」「片頭痛」「群発頭痛」の3種に大別されます。
「緊張型頭痛」は、長時間のパソコン作業など同じ姿勢を長く続けたことによって肩や首の筋肉に負担がかかることが原因で起こり、「筋緊張型頭痛」とも呼ばれます。
「片頭痛」「群発頭痛」は頭・脳周辺の血管が関与するものです。
緊張型頭痛と片頭痛は混在する人もいます。
脳の病気に伴う頭痛
「髄膜炎」「脳腫瘍」「脳出血」など脳の病気が原因で起こる頭痛です。
嘔吐や麻痺などほかの症状も起こることが多く、命に関わります。
頭痛の症状
緊張型頭痛
- 頭が締めつけられるような重い痛み
- 首や肩のこりを伴う
- 軽いめまいを伴うことがある
- 1日中痛みが続く
片頭痛
- ズキンズキンと脈打つような強い痛み
- 吐き気を伴うことがある
- 音や光に敏感になる
- 体を動かすと頭に響く
- 光がピカピカなど幻覚がある
群発頭痛
- 目の奥がえぐられるような激痛
- 夜中から明け方に痛むことが多い
- 1回の痛みは、15分~3時間程度
- 1~2カ月の間に集中してほぼ毎日起こる
脳の病気に伴う頭痛
- 頭を殴られたように激しく痛む
- 吐き気・嘔吐を伴う
- 手足に麻痺やしびれがある
- ろれつが回らない
- もの忘れ
当院での治療

まず問診で、いつ頭痛が起き、どのような痛みで、どのくらい続くのかなど、症状の発症形態を患者さんから伺います。
その後、神経学的な検査を行い、頭の中の病変が疑われる場合は、MRI、CTなどの画像診断を行います。
慢性頭痛の場合は、主に鎮痛剤を処方します。片頭痛には片頭痛専用の内服治療薬があります。
緊張型頭痛の場合は、当院で導入しているウォーターベッド型マッサージ器、マイクロ波治療器、高周波治療器、レーザー疼痛治療器等を用いた理学療法も効果が期待できます。
頭痛の種類によって治療法が違うため、的確な診断を行うことが重要です。
脳の病気に伴う頭痛の場合は、ほとんどが入院治療外科的治療を必要とするため、入院の設備が整った信頼のおける連携医療機関をご紹介いたします。
よくある質問
- Q
頭痛のときに市販の鎮痛薬をよく飲みます。飲み続けても大丈夫でしょうか。
- A
頭痛のときは我慢せずに薬は飲んでよいと患者さんにはお伝えしています。
頭痛が続くとストレスになり、悪化することがあります。
ただ、薬がだんだん効かなくなり、薬を飲む回数や量が増えたのに頭痛が一向に改善しない場合には、薬剤の使用過多による頭痛を起こしている可能性があります。
毎日のように飲んでいる鎮痛薬が、頭痛の原因になっている方も多いのです。
自己判断にまかせず、一度、医師の診察を受けましょう。
- Q
日常生活でできる頭痛対策を教えてください。
- A
緊張型頭痛は、首や肩の筋肉のこりが原因ですから、入浴で温めたりストレッチを行って、血行をよくすることでやわらぐことがあります。
一方、片頭痛は、できるだけ早く、片頭痛用薬を服用する必要があります。
さらに光や音の刺激を避け、静かで暗い場所で安静にするようにしましょう。
- Q
頭痛持ちは遺伝しますか?
- A
3つの慢性頭痛のうち、「片頭痛」には遺伝性があると考えられています。
特に母親が片頭痛だと子どもも片頭痛になる可能性が高くなります。
ただし、遺伝ではなく家族は同じ生活環境で暮らしていますから、頭痛になりやすい生活環境であるということも考えられます。